|


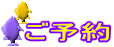
2013年 企画原稿
開拓村を襲った世界最大のヒグマ事件
「熊嵐」 倉持 武 著
isbn978-4-903847-44-3 \1,365 円(税込)
熊 嵐
序 章
この物語は、一九十五年(大正四年)の十二月九日から十四日にかけて、北海道苫前郡苫前村(現在の苫前郡苫前町古丹別三渓)の開拓村(通称六線沢)で、実際に発生した世界最大の熊害事件を素材にして書かれたフィクションである。
この事件は、身の丈三・二メートル、体重五百キロの巨大ヒグマに開拓村が襲われ、なんと七名が死亡し、三名が重傷(後に一人が後遺症で死亡)を負うという前代未聞の大熊害事件であった。
だが、発生以来約百年の年月が経過し、当時この事件に直接関わった人々は、もうほとんどこの世にはいないとあって、これほどの大惨事でありながら人々の記憶から消え去ろうとしている。だが、これだけの大惨事を、単なる一地方の熊害事件として時間の経過を理由に風化させてしまってもいいものだろうか? それでは、あまりにも悲しすぎる。厳しい環境の中で、逞しく生きる開拓村の生き様と、この熊害事件がもたらした惨状を併せ持って、この事件を永遠に語り継ぎたいものである。
一 開拓村
大正四年も、はや十二月。今年も残すところあと僅か。いよいよ年の瀬も押し詰まり、正月を間近に控えて、北海道苫前郡苫前村(現在の苫前町)地方は、連日台風並みの強風と豪雪に見舞われていた。
苫前村から四里(約十六キロメートル)ほど内陸部(東方)に入ったところに、古丹別の集落がある。更にこの集落から南方に向かって五里(約二十キロ)ほど三毛別川沿いに遡ったところに小さな開拓部落がある。この集落を、土地の人々は通称「六線沢」と呼んでいる。
この辺りは、元来が御料地(政府の直轄地)で、一面手付かずの原生林が広がっていた。それが政府の北海道開拓政策の推進によって、明治末から大正の初期にかけて主に東北地方からの入植者が入り込み、あちらこちらに開拓部落が次々と誕生した。六線沢もそんな中の一つである。
この地の正式な名称は、北海道天塩国苫前郡苫前村大字力昼村三毛別御料農地六号新区画開拓部落六線沢という。山間部を蛇行して流れる三毛別川の川沿いに、一里半(約六キロ)に渡って十五軒(巻末の資料参照)が転々と軒を連ね、川沿いに広がる僅かな台地にへばりつくようにして生活していた。
当初政府側は、「この土地は大変肥沃な土壌で、農業をするには最適な土地である。しかも、水資源が豊富で農業条件は頗る良い」と宣伝していた。
ところが、実際に入植してみると、その実情はまったく逆。まず農業用地として利用できる平地は、川沿いにほんの僅かしか開けていない。しかも、その土地は極端にやせ細り、とても農作物が満足に育つ状況にはなかった。これには、希望に燃えて入植した住民たちも、一様にがっくり。即「話が違う」と立ち上がった。しかし、その声は政府までは届かない。そこでやむをえず、彼らはその矛先を周囲の原生林の開墾に向けた。
連日巨木を切り倒してはその根っこを馬に引かせて掘り起こし、鬱蒼(うっそう)と生い茂る潅木や蔦類、更に密生するブッシュの類を刈り取り、家族総出で朝から晩まで全身全霊を投入。まさに筆舌に尽くせぬ大変な作業の連続に明け暮れた。そのあまりの過酷な重労働に、いつしか精も根も尽き果てて、心身ともにボロボロになり、途中で挫折して離村を希望する者も続出した。希望に満ちた六線沢集落も、いつしか崩壊寸前まで追い込まれた。
この地は、気候的にも厳しいが、それ以上に周辺の原生林に生息する野生動物による農作物への被害も甚大だった。種を撒く傍から野鳥がそれを啄ばみ、やっと発芽したばかりの若苗を、今度はエゾシカの大群が根こそぎ食んでしまう。これではいかに懸命に働いても、生活の安定はまず望めない。当然ながら、住民たちの日々の生活は困窮を極めた。
こうなると、口から出るのはため息と政府に対する不満ばかり。いつまでたっても抜け出せない悪循環に、誰もが苛立ち、いつも不満と怒りが胸の内でブスブスと燻っていた。
更に、日ごろ満足に栄養も摂れないまま連日重労働に勤しむ住民たちは、文字通りガリガリに痩せ細り、まさしく骨と皮ばかり。目玉ばかりがギョロギョロと異彩を放ち、歯は抜け落ち、皮膚は真っ黒に変色。見るからに異様な顔相に変貌した。
ここまで身をすり減らし、砂を噛むような極貧に喘ぎながらも、彼らはこの地を離れられない。他に行くところがないのだ。今更故郷にも帰れない。よしんば帰ってみたところで、そこには自分たちの居場所はない。この現実の前に、一旦燃え上がった離村への執着心もいつしか萎え、(自分たちは、この地に骨を埋めるしかない)と自覚するに至った。こうして日々悶々としながら、入植以来苦難の五年が過ぎた。
時間の経過とともに、住民たちの気持ちも次第に落ち着き、やっと顔の強張りも取れ、血走った目に柔和な光が蘇った。それからはお互いに声を掛け合い、積極的に各家庭を行き来し、午後の一時を茶のみ話に花を咲かせるまでになった。こうして、これまでバラバラだった十五軒が、ここにきて恰も一家族のような和やかさでしっかりと纏まった。
当初はぎくしゃくとしていた人間関係も、今やまるで先祖の代からの知己のような親密さ。連日晴れやかな笑い声が至る所で聞かれ、人々の表情も極めて明るい。ここまでくるには、まさに死の苦しみの連続だった。だが、今にして思えば、そのすべてが『産みの苦しみ』だったのかもしれない。
ところで今日は十二月の八日。今年も残すところあと二十日あまり。もうすぐ正月がやってくる。これまでは、その日を生きるのに精一杯で、とても正月らしい正月は迎えられなかった。だがここに来て、生活は依然として厳しいものの、気分的にはかなりの余裕が出てきた。子供のいる家庭では、今年は子供たちに晴れ着の一枚も買ってやりたいと、豪雪の中での材木の切り出しに男衆は夢中で勤しんでいる。一方、女たちは臼や杵を出して洗い、餅つきの準備に取り掛かった。子供たちは、指折り数えて正月を待っている。
この辺りは山間部とあって、冬季の日照時間は極めて短い。午後の三時を回れば辺りはもはや夕暮れ時。自然が相手の生活は、朝、太陽とともに一日が始まり、日没を以って一日が終わる。その後は、囲炉裏を囲み家族全員で火に当たりながらの一家団欒。これが一日の中で最も楽しい時間帯。日ごろこれといった娯楽のない開拓生活では、こうして談笑しながらの夕食が、唯一の娯楽となる。この時ばかりは、老いも若きもない。みんな一緒になって囲炉裏を囲み、冗談を飛ばし合いながらワイワイ、ガヤガヤ。時には腹を抱えての大笑い。そして囲炉裏に架けられた鍋をみんなで突っつき会う。こうした肌と肌との語らいが、家族の絆をしっかりと結びつけ、自然な形で不屈の精神を育み、それを親から子へ、そして子から孫へと確実に受け継がれていく。
開拓農家にとって子供は貴重な宝であり、同時に重要な労働力でもある。この地区では、小学校就学前の幼い子供たちも、親たちと一緒になって朝から晩までよく働く。この年代にして、早くも自分の使命を弁え、将来の夢を開拓に向けている。これらの精神は、すべてこの一家団欒の食事の中で育まれる。
|